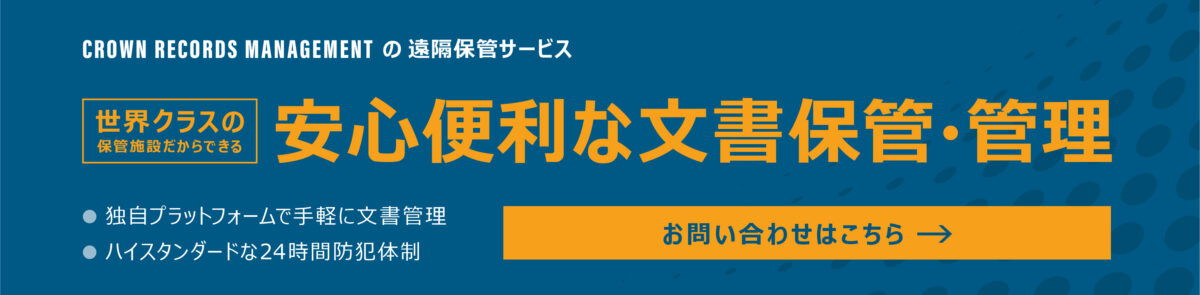「保管」と「保存」は、用語が似ているため混同しやすい言葉です。書類における保管と保存は文書管理の一環ですが、それぞれ目的とやり方が異なります。適切に文書や資料を扱うには、この違いを理解しておくことも大切でしょう。
今回は、書類管理における保管と保存の意味と、それぞれのやり方をまとめました。現在整理しているものの扱い方や、書類の管理状態を移行するタイミングなども紹介します。
書類管理における保管と保存の違い
書類管理における保管と保存の違いを解説します。それぞれの言葉の意味と目的を理解することで、より適切な方法を選びやすくなるはずです。
保管とは
書類における保管とは、使用頻度の高い書類や資料を紛失・破損から防ぎつつ、取り扱いやすい環境で管理することです。
業務上で頻繁に活用する文書や資料、それを収納しているファイルに対しておこなわれます。ファイル自体も事務所内など、業務上取り出しやすい場所に収納されます。会社や業務ごとに扱う書類は変わり、作成・発生から1年前後の書類に適応されることが多い管理方法です。
保管扱いにすべき書類は、主に以下の5つに該当するものです。
- 今年・今年度文書
- 前年・前年度文書
- よく活用する文書
- 数年にわたって常用している文書
- 使用頻度は低いがまれに活用する文書
特徴を見ると、すべて業務でよく活用する可能性が高いものが該当していることが分かります。業務上よく閲覧・活用する書類は、基本的に保管扱いになると覚えておきましょう。
関連記事:会社における書類保管の流れは?保管上の注意点についても解説
保存とは
書類における保存とは、使用頻度の低い書類を現状維持しておく管理状態のことです。
個人情報や経理関係の書類は、法律上一定の保管期間が決められています。これらの中には、会社が存在する限り管理し続けなくてはならないものもあります。また、業務により昔の資料を閲覧・持ち出しながら行う場合もあるでしょう。
このような文書や資料は、変更してはならない、またはめったなことがない限り更新されないため、現状維持で管理されます。これが保存です。
保存された資料は管理扱いのものとは異なり、事務所以外の場所で扱われます。書個室や専用の倉庫で管理するのが一般的です。
保存すべき書類を見分ける条件は、以下のふたつです。
- 保管条件に該当しない文書
- 法律で保存期間が定められている文書
保存する書類は、保管の条件を外れたものが該当するため、「保管扱いになる書類の種類」さえ知っていれば簡単に見分けられます。業務で必要なくなった書類は、保管から保存に移行する形です。
なお、法律上保存期間が決まっている書類や資料もある点には注意が必要です。
書類の保管方法
一般的な書類の保管方法を解説します。使用頻度の高い書類や社内で共有して使う資料は、活用しやすい形で管理するのが基本です。
保管対象の書類を決める
まずは保管対象となる文書の条件を決めます。あらかじめ保管する物のルールを決めておけば、分類するとき、困る事態を予防できるはずです。まずは先ほど解説した条件に合致する書類や、業務上必要な書類を洗い出しましょう。
業務上必要な文書や資料は、時間がたつと必要とされなくなるものもあります。これらの文書をそのまま保管し続けると、業務をおこなう場所に使用頻度の低い文書が混在しやすいです。これでは必要なものを探すたびに、多くの時間と手間をかける事態になりかねません。
このような事態を避けるためにも、ルールを決めるときは保管条件だけでなく、保存に移行する条件も決めておきましょう。
保管対象書類を分類する
文書や資料のルールを決めたら、対象書類を集めましょう。まずは管理する場所に書類を集めてから、分類作業を行います。
分類は社内業務に従って行います。まずは使用頻度や業務内容ごとに分類し、その中でジャンル・担当別に分けていきましょう。
なお、このとき分類の仕方が分からないものが出てきたら、一時管理用の箱に入れます。この箱の中身が大量にある場合、分類がきちんとできていない可能性が高いです。箱がいっぱいになるようなら、再度分類しましょう。
ファイリングしてラベルを貼る
文書や資料を分類したら、分類ごとに収納先を用意します。以下のアイテムを活用しましょう。
- ファイルボックス
- ファイル
- ラベル
文書や資料は分類ごとにひとつのファイルにまとめ、内容を明記したラベルを貼りましょう。ラベルに記載する内容は、一目で何が入っているのかわかるようなものを書くのがポイントです。
ファイリングしたらファイルボックスに収納します。ラベルが見えるように、縦置きで管理しましょう。複数担当者がいるなど、共有して使うファイルはキャビネットやロッカーに収納すると使いやすくなります。収納する際は書類を必要とする人が使いやすいかを意識しながら考えましょう。
書類の保存方法
一般的な書類の保存方法を解説します。保存は保管とは異なる方法で管理するため、管理方法を混同しないよう注意しましょう。
保存に移行する書類をまとめる
保管している書類の中には、条件から外れるものが定期的に出てきます。これらの中には、法律や社内ルールで一定期間保存しなくてはならないものもあるはずです。該当する書類をまとめておきましょう。
書庫室にしまうか専門の保存業者に預ける
まとめた書類は、事務所等とは別の場所で管理します。管理方法は複数ありますが、よく使われているのが以下のふたつです。
- 書庫室や倉庫にしまう
- 文書や資料保存の専門業者に管理を委託する
管理ルールは会社ごとに異なりますが、個人情報や金融機関の情報などの機密文書は、法律で定められた管理方法を用いなくてはなりません。場所も取りやすいことから、専門業者に預ける企業も多いです。
管理する文書や資料が膨大なところだと、一度書庫室や倉庫に一定期間保存した後、業者に任せるなどの手順を取っているところもあります。
保存すべき期間を過ぎたら破棄する
保存期間が決まっている文書や資料は、期限が過ぎたら破棄します。管理スペースにも限界があるため、適切に保存するには定期的に破棄しなくてはなりません。これは、保管・保存共通のポイントでもあります。
不要な書類で収納スペースが圧迫されていると、必要なものを探すのが困難になります。保存すべき期間を過ぎたものは、きちんと破棄しましょう。なお、文書や資料の中には破棄してはならないものや、破棄の仕方も法律で定められているものがあります。文書や資料を整理する際は、これらの扱いにも注意しながら取り組みましょう。
まとめ
書類における保管と保存は似ているようで意味や管理方法が異なります。混同すると、業務で使う文書や資料の管理が難しくなりがちです。
保管と保存は一度行えばよいものではありません。業務の流れに合わせて、書類の管理状態を移行する必要があります。定期的に管理状態の見直しと整理を行い、適切に管理されている状態を維持しましょう。